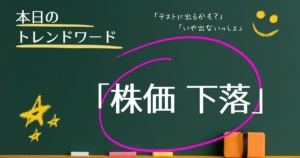初心者が株式投資を始める場合、現物取引から始めるよう勧められることが多いですが、その理由は何でしょうか。なんとなく「信用取引はやめておいたほうがよい」と思うものの、その理由まで明確に知っている人は多くないかもしれません。
そこでこの記事では、株式の現物取引と信用取引の違いや、信用取引はやめておいたほうがよい理由、現物取引と信用取引の使い分け方について解説します。
これから株式投資を始める際にぜひ参考にしてください。
株式の現物取引とは
まず現物取引とは、自分の資金で株式を購入し、その株式を保有する取引方法のことです。例えば、ある会社の株を100株購入した場合、あなたはその会社の株主になります。この株主権を活用して、配当金を受け取ったり、株主優待を楽しんだりすることができます。
現物取引の最大の特徴は、リスクが自分の資金の範囲内に限定されることです。投資額以上の損失を負うことがないため、投資初心者でも安心して始められる取引方法といえます。
また、購入した株式は売却するまで自分の資産として保持されるため、長期投資にも適しています。
株式の信用取引とは
次に信用取引とは、証券会社から資金や株式を借りて行う取引のことです。これにより、手元の資金以上の取引が可能になり、少ない資金で大きな利益を狙うことができます。具体的には、信用取引では一般的に手元資金の最大3.3倍までの取引が可能です。
信用取引には主に以下の2種類があります。
- 一般信用取引:証券会社が独自に条件を設定する信用取引。取引期間や金利が比較的自由に設定されている
- 制度信用取引:証券取引所が定めたルールに基づいて行われる信用取引。期間や条件が統一されている
信用取引では「買い」だけでなく「売り」から取引を始めることもでき、相場の動きに対して柔軟に対応できる点が魅力です。
株式の現物取引と信用取引の違い
では、株式の現物取引と信用取引にはどのような違いがあるのでしょうか。主な違いは以下の3点です。
レバレッジをかけられるかどうか
| レバレッジの有無 | |
| 現物取引 | なし |
| 信用取引 | あり(最大3.3倍) |
レバレッジとは、少額の資金で大きなリターンを得られるような仕組みのことです。
現物取引では、自己資金の範囲内でしか取引を行うことができません。一方、信用取引ではレバレッジを利用して、自己資金の数倍の取引が可能です。具体的には、差し入れた資金(証拠金)の、最大約3.3倍まで取引ができるようになります。
「売り」から取引が始められるかどうか
| 取引の方法 | |
| 現物取引 | 「買い」から始める取引のみ |
| 信用取引 | 「買い」からも「売り」からも取引できる |
現物取引では、株式を購入するところ、いわゆる「買い」から取引を始めます。一方、信用取引では前述のとおり「買い」だけでなく「売り」から取引を始めることもできます。これを「空売り」といいます。
売りから取引することで、価格が下がることを前提とした取引を行うことができ、下落相場でも利益を得るチャンスが広がります。
1日に同じ銘柄を何度も取引できるかどうか
| 同銘柄の取引制限 | |
| 現物取引 | 1日1往復まで |
| 信用取引 | 制限なし |
現物取引では、同じ銘柄を1日1往復(買い+売り)しか取引できないという制限があります。
一方の信用取引では、同じ銘柄を同日に何度も取引することができます。つまり「回転売買」が可能です。これにより、1日に何度も同じ銘柄から利益を出すことが仕組み上可能となります。
どのような手数料がかかるか
| 主な手数料 | |
| 現物取引 | 売買手数料 |
| 信用取引 | 金利、貸株料、品貸料(逆日歩)、名義書換料、事務管理費など |
取引にかかる手数料体系にも違いがあります。現物取引の場合、日本株の取引であれば原則、売買手数料しかかかりません。一方の信用取引では、金利や貸株料などさまざまな手数料がかかる可能性があります。
| 信用取引にかかる主なコスト | |
|---|---|
| 名称 | 概要 |
| 金利(信用金利) | 証券会社からお金を借りるためのコスト。 「買い」から始める取引で発生 |
| 貸株料 | 証券会社から株を借りることに対するコスト。 「売り」から始める取引で発生 |
| 品貸料(逆日歩) | 株を「売り」から始めた人が「買い」から始めた人に対して払うコスト。 「売り」から始める取引では支払い、「買い」から始める取引では受け取る可能性がある |
| 名義書換料 | 決算日(権利確定日)をまたいだ場合に発生するコスト。 「買い」から始める取引で発生 |
| 事務管理費 | 「買い」や「売り」を入れて1カ月経過するごとにかかるコスト。 「買い」「売り」どちらでも発生 |
「信用取引はやめておけ」と言われる理由
多くの利益を上げるために、初めから信用取引に挑戦しようとする投資初心者も少なからずいます。しかし一般的に、投資初心者は信用取引はやめておいたほうがよいです。その理由を説明します。
追証が発生するリスクがあるから
「追証(おいしょう)」とは、信用取引で株価が大きく変動し、担保として差し入れている証拠金が不足した際に、追加で入金を求められる制度です。
例えば、100万円の資金で300万円分の株式を購入した場合、株価が急落して保有資産の価値が200万円を下回ると、証券会社から追証の請求を受けることになります。これを支払えない場合、強制的に株式が売却され、さらに損失が拡大するリスクがあります。
この追証を支払うために借金する投資家も稀にいますが、これはさらに損失を広げる可能性をはらむ非常に危険な行為のため、避けるべきです。
空売りによって大きな損失を出す可能性があるから
空売りは、価格が下がると利益を得られる取引方法です。しかし、予想に反して株価が上昇すると、損失が無限に膨らむ可能性があります。
また、そもそも空売りを行う際は、損切りするタイミングを明確に決めておくことが重要ですが、損切りに私情を持ち込んでしまうこともあります。特に初心者は相場の動きを正確に予測することが難しく、こうした決断にも慣れていないため、大きな損失を招くリスクがあるのです。
金利や貸株料などの手数料が発生するから
信用取引では、借りた資金や株式に対して金利や貸株料が発生します。これらの手数料は、取引を継続するほど積み重なり、利益を圧迫します。短期的に利益を上げられない場合、手数料の負担が大きくなり、結果的に損失が増えることもあります。
現物取引・信用取引の使い分け方
投資初心者はまず現物取引から始めたほうがよいものの、いずれ信用取引に挑戦する機会があるかもしれません。その際には、次のような観点で取引手法を使い分けてはいかがでしょうか。
配当や株主優待目的、NISA口座なら現物取引
株式を保有していると、配当や株主優待が受け取れることがあります。この配当や株主優待は、現物の株式を保有している「株主」が対象です。しかし信用取引ではこの株主に該当しないため、配当や株主優待目的で取引するなら現物取引を選択しましょう。
また、NISA口座ではそもそも信用取引が利用できないため、現物取引が唯一の選択肢となります。
デイトレードなど短期売買目的なら信用取引
デイトレードなどの短期売買を目的とする場合は、回転売買が許されている信用取引が向いています。レバレッジを活用することで、少ない資金で効率的に利益を狙えるでしょう。
ただし、前述の通り追証や空売りによるリスクがあるため、資金管理や取引管理を徹底することが重要です。
まとめ
株式の現物取引と信用取引には、取引の方法やレバレッジ、手数料体系などさまざまな違いがあります。初心者はまず現物取引で投資の基礎を学び、安全に経験を積むことが大切です。正しい知識と戦略を持ち、リスクを抑えながら資産運用を行いましょう。

執筆者:金指 歩(かなさしあゆみ)
株式会社となりの編プロ 代表取締役・編集者・ライター。大学卒業後、大手信託銀行に4年半勤務。住宅ローンや投資信託、法人向け預金商品の営業を担当。その後、不動産関連会社、証券会社、ITベンチャーを経て、2017年12月よりライターとして開業。2023年12月に法人化。主に金融・ビジネス・人材系のコンテンツ制作に携わっている。
<このメディアについて>
『となりの資産運用』は、資産を増やしたいすべての人に向けて、投資や資産形成などお金に関する全般的な知識、情報をわかりやすくお伝えしているメディアです。ぜひ他の記事も併せてご覧ください。
<注意事項>
このメディアは、読者の皆様へ継続的に無料で良質な情報をお届けするため、広告による収益モデルを活用しております。
記事の内容に合わせ、読者の皆様が特定のバナーをクリックした際に当社へ報酬が支払われる「ディスプレイ広告」、本サイトを通じて一定の成果地点(証券口座開設など)へ到達した際に当社へ報酬が支払われる「成果報酬型広告」等を扱っています。
扱う広告によって記事の内容が不当に変更されることはございません。