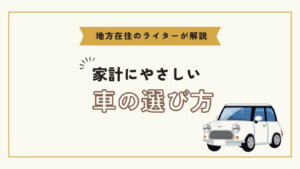医療保険やがん保険は、万が一の病気やケガに備えるために有効な対策のひとつです。しかし、保険の仕組みや保障内容が複雑なものも多く「どれを選んでいいのか分からない!」と思っている人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、医療保険・がん保険の選び方や注意点について解説します。自分にとって必要な保障はなにか、考えるきっかけにしていただけるとうれしいです。
医療保険・がん保険選びはなぜ難しいの?
医療保険・がん保険選びを「難しい」と感じてしまうのは、どのような理由があるからでしょうか。考えられる3つの要因を説明します。
保険の目的が広く・あいまいになりがちだから
そもそも保険は、その役割ごとに大きく3つに分けられます。
- 死亡した場合の保険
- 医療・ケガに備える保険
- 貯蓄のための保険
死亡保険や貯蓄性の高い保険は「亡くなった場合に備えるため」「お金を貯めるため」と目的がはっきりしています。当面の生活費やお葬式にかかるお金など、備えておきたい金額も比較的予想しやすいでしょう。
一方、医療保険やがん保険は上記と比べて「どんな病気やケガを想定したらいいのか」「いくらあればいいのか」など、完ぺきに予想するのが難しいと言えます。多くの可能性を思い浮かべながら保険を選ばなくてはいけないため、難しさを感じてしまいます。
保険会社や保険代理店など窓口の種類が多いから
医療保険やがん保険を提供する保険会社は数多くあります。さらに、保険代理店や保険ショップ、ファイナンシャルプランナー(FP)など、保険を扱う窓口もさまざまです。選択肢が多すぎると思いませんか?
保険会社ごとに特徴や得意とする分野が異なるため、契約内容や保障される範囲を比べるだけでも相当な時間と労力が必要です。選択肢が多くて悩むだけでなく、各商品について理解するのも難しくなります。
保険特有の専門用語が多いから
これは他の保険商品にも共通しますが、保険について知ろうとすると「解約返戻金」「免責期間」「払込免除」など、日常生活ではあまり馴染みのない言葉が次々と登場します。保険を契約した人のなかには、これらの意味を理解しないまま契約してしまった人もいるのではないでしょうか。
専門用語はしっかりと理解しないと誤解が生じやすく、後にトラブルや予期せぬ事態を招く可能性があります。難しい用語が多いのも、保険選びを難しく感じさせる要因のひとつです。
医療保険・がん保険の選び方
ここからは、実際に医療保険やがん保険を選ぶときにチェックしたいポイントをご紹介します。
保障期間と払込期間で選ぶ
医療保険やがん保険はその保障期間によって「定期保険」と「終身保険」に大別されます。定期保険は、保険料が比較的割安な反面、契約の更新時に保険料が上がりやすいのがネックです。
一方の終身保険は、生涯にわたって保障が続き、年齢が上がっても保険料が変わらないため安心感がありますが、定期保険に比べると保険料が割高となっています。
払込期間には「短期払い」と「全期払い」があり、短期払いは期間が短いぶん、月々の支払額が大きくなりますが、早期に払い込みが終わります。全期払いは毎月の支払額を抑えられるため、支出を長く分散させたい場合に向いている選択肢です。
似たような保障内容でも、保障期間と払込期間の組み合わせによって支払金額が異なりますので、保険を比較するときに必ず確認しましょう。
入院したときの保障で選ぶ
医療保険やがん保険には、入院した際に日額で給付金が支払われるタイプがあります。
たとえば、1日あたりの支給額が高く、支給日数の上限が多い保険は保険料が高くなりますが、長期入院に備える安心感が得られます。反対に、日額の給付金を抑えれば家計への負担は軽減できるでしょう。
保険を選ぶときは、「1日あたりの支給金額」と「支給される入院日数」がポイントです。
手術時の保障で選ぶ
医療保険には、手術時の保障も含まれていることが一般的です。手術一回につき決まった金額が支払われるタイプのほかに、手術の内容や給付金の日額に応じて給付金額が異なるものもあります。
また、がん保険には診断時にまとまった金額が支払われるタイプもあり、手術や治療の種類によって給付額が変動するため、支給条件をしっかりチェックしてくださいね。
私はこう選んだ!30代女性、子育て家庭の保険選び
はじめにお伝えしたいのが「保険の選び方に正解はない」ということです。家族構成や年齢、収入などによっても違いますし、なにより、安心できる保障内容は人それぞれです。そのうえで、考え方のひとつとして参考にしていただけたらと思います。
2024年現在、加入している医療保険・がん保険は次の通りです。夫婦それぞれで同じ保険に加入しています。
がん保険
・診断時に一時金50万円。
・入院給付金日額5,000円。
・抗がん剤治療一回ごとに10万円
我が家の保険はとてもシンプルですが、このような選択になるまでにはいくつかのきっかけや考え方の変化がありました。どのような経過を経たのかをお伝えします。
収入源が1人のときは保険を手厚く、2人なら貯蓄優先
出産後、数年間は専業主婦だったので、夫1人で家計を支えていました。子どもが小さいころは貯蓄も思うようにいかず、当時は夫の収入だけが頼りです。夫は会社員で社会保険にも加入していましたが、もしものことを考えると不安でした。
結婚当時に知り合いを通じて加入した医療保険は内容が充実していたものの、そのぶん支払いも苦しく、八方ふさがりのような感覚だったことを覚えています。
その後、共働き家庭になり、当面の生活費が貯まったタイミングで夫の医療保険は解約しました。保険の見直しを考えるなかで、「医療保険で医療費のすべてをまかなう必要はない」と感じ始めたのがきっかけです。解約後も家計からは同じ金額を貯蓄に回すことで、保険に代わる安心を積み立てています。
また、共働きによって「どちらかが一時的に働けなくなったとしても、もう片方が収入を補える」と考えられるようになったのも大きな変化でした。
とはいえ、現在の保険はあくまで現在の状況に合ったものです。定期的に見直す必要があると感じていますし、なにかの事情でシングル家庭になる場合は、公的な手当や子供の教育費も考えながら、医療保険や収入保障の保険をもう少し充実させるかもしれません。
がん保険に加入しているのは、親しい人が闘病していたから
医療保険は解約しているのにがん保険だけ加入しているのは、身内ががんで亡くなっているからです。
近年、がん治療の平均入院日数が短くなり、令和2年の調査では19. 6日(※)という結果が出ています。「思ったより入院期間が短い」と思う方も多いのではないでしょうか。
長期入院の可能性が低いなら、がんの治療費も現金で備えたいと思う反面、私も夫もがん保険はなかなか解約する気持ちになれません。保険選びには、過去の経験や不安感が大きく影響することを身をもって体験しています。
現在加入している保険の保障内容はとても小さく、実際にがんになれば給付金だけではまかなえません。それでも、お守り代わりとして今後もしばらく続けていく予定です。
※厚生労働省「令和2年(2020)患者調査」3 退院患者の平均在院日数等
「貯蓄」「死亡保険」「医療・がん保険」の役割をしっかり分ける
我が家は、死亡保険とがん保険に夫婦それぞれひとつずつ加入しています。死亡保険とがん保険はできるだけコンパクトに、最低限の保障にまとめ、できるだけ貯蓄に回すようにしています。
保険商品のなかには、貯蓄と保障がセットになったものや、死亡時だけでなく医療保険も付帯した商品も多くありますが、我が家の選択肢からは外しました。「年齢や家庭状況に合わせて常にカスタマイズしたい」というのが理由です。自分の判断で、好きなタイミングで保険を見直すなら、小さな保険を組み合わせる方法が私には合っています。
また、貯蓄を優先しているのは「使い道に融通が利くから」です。貯めたお金は病気やけがに備えてもいいし、教育費にしてもいいですし、もしかしたら老後費用になるかもしれません。
今後も「自分に必要な保障は何か」を定期的に見直し、貯蓄と相談しながらベストな保険選びをしていきたいです。
医療保険・がん保険選びの注意点
最後に、これから医療保険・がん保険を選ぶ方に知ってほしいポイントを以下の2点にまとめました。
「今の生活」と「未来の保障」のバランスに気を付ける
病気やケガのリスクに備えることは大切ですが、毎月の生活費や家計に大きな負担をかけてしまうのは避けたいところです。
保険料は生活に無理のない範囲におさえつつ、必要最低限の保障を確保することが、長く保険を続けるコツといえるでしょう。現在と未来の両方で豊かに過ごせるバランスを見つけてくださいね。
公的な保障も確認しておこう
不安や恐れが大きいと、冷静な判断ができなくなることがあります。不安なまま保険選びを始めてしまうと、保険をかけすぎてしまう可能性があるので注意が必要です。
医療やがんに関しては、公的な保障を受けられるケースもめずらしくありません。健康保険、高額療養費制度、傷病手当金など、自分が受けられる医療制度を確認し、「もしものときに『保険』で備えたいのはいくらか」という視点で保障内容を検討しましょう。
【編集部追記】
2024年12月25日、医療費の支払いが高額になる患者の自己負担を一定額に抑える「高額療養費制度」について「2025年8月から上限額を段階的に引き上げることが決まった」と報道されました。所得が高い人ほど自己負担額が現状よりも高額になる可能性があるため、最新情報を確認してみてください。
まとめ
家族構成や収入、年代などによって必要な保障は異なりますが、どの方にも大切なのは、「保険の内容が分からないまま契約しないこと」です。家族が安心して今を過ごせて、将来のもしもにも備えられる選択肢が見つかるまで、保険商品の中身まで比較し、じっくり検討してみましょう。
-1024x946.jpg)
執筆者:いしかわ りの
赤字家計になったことをきっかけに、家計管理に目覚めたWebライター。支出を見直し、貯金ができる仕組み作りに成功した。多趣味かつオタク気質なため、さまざまなお金の誘惑と日々戦っている。
<このメディアについて>
『となりの資産運用』は、資産を増やしたいすべての人に向けて、投資や資産形成などお金に関する全般的な知識、情報をわかりやすくお伝えしているメディアです。ぜひ他の記事も併せてご覧ください。
<注意事項>
このメディアは、読者の皆様へ継続的に無料で良質な情報をお届けするため、広告による収益モデルを活用しております。
記事の内容に合わせ、読者の皆様が特定のバナーをクリックした際に当社へ報酬が支払われる「ディスプレイ広告」、本サイトを通じて一定の成果地点(証券口座開設など)へ到達した際に当社へ報酬が支払われる「成果報酬型広告」等を扱っています。
扱う広告によって記事の内容が不当に変更されることはございません。